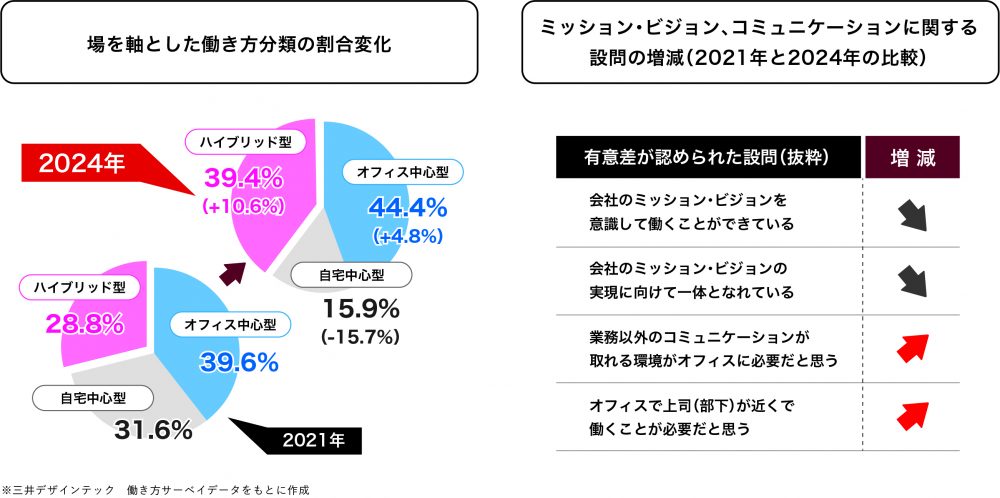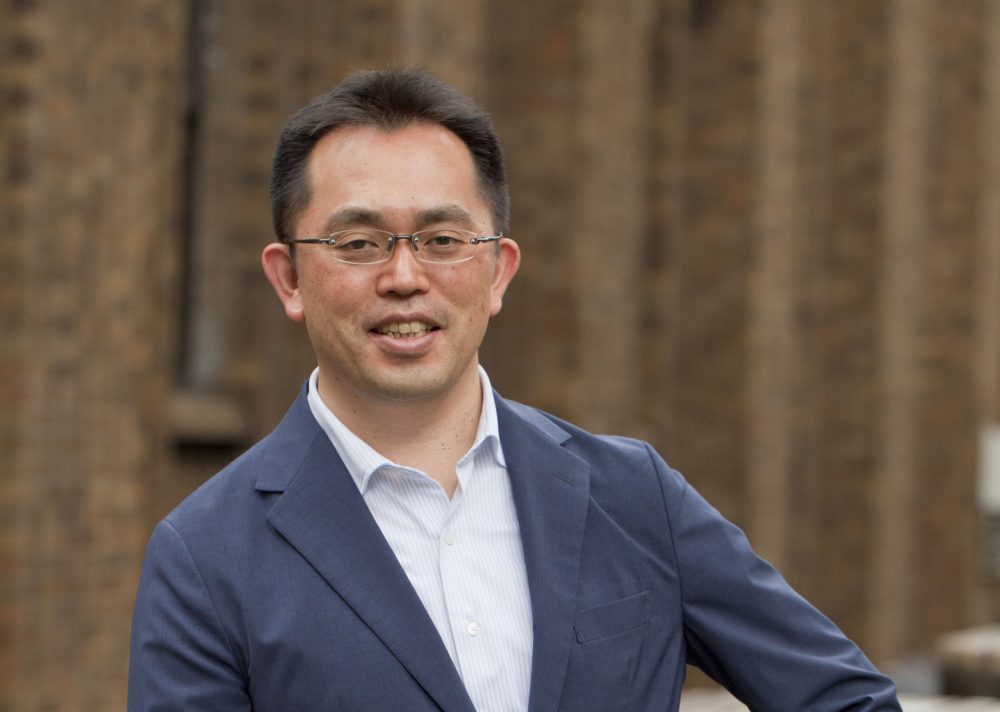- contents
-
- Future Articles
- New Relationships
- Offistyle+
Future Articles
- vol.20
-
プロフェッショナルがリビングに集う。
そこから時代を拓く創造が生まれる。
2024年に創立50周年を迎えた三井ホームは、次の50年を見据え
三井ホームグループ5社を1つのオフィスに集約することを決めた。
各社の連携をもっと深め、これまで以上のクリエイティビティを発揮するために
新オフィスはどうあるべきか。
プロジェクトチームが導き出した答えは「リビング イン アクセス」。
家づくり、街づくりのプロフェッショナルがコミュニケーションを深め
ディスカッションし、新時代を創造する場所
皆が気持ちよく集える“リビング”こそが必要だった。

地球環境の変化が問題となる今「木の建物」が見直されている。先進技術でつくられる木造建築は環境負荷が少なく、人々の健康にも寄り添うことができるからだ。住宅にとどまらず病院、学校、商業施設まで木造建築において業界屈指の実績をもつ三井ホームグループは2024年、培ってきた木造建築技術を総称したブランド「MOCX(モクス)」を立ち上げ、これからの脱炭素社会に向けてあらゆる建物の木造化に挑戦し、地球の未来に大きく貢献していく方針を示した。グループとしての方針が明確に打ち出されるなか、取り組むべき課題が浮かび上がる。グループ5社※のコミュニケーションと新時代の働き方だ。
三井デザインテックで営業を担当する鈴木達也氏は、新木場オフィスにグループ5社を集約することになった経緯を振り返る。
「もともとはオフィスの改装を手がけるだけの予定でした。しかし話を進めていくうちに、グループ5社の繋がりをもっと強めたいという池田社長の想いが高まり、グループ全体で約800人規模の社員を集約できる場所を探すことになったのです」
新木場センタービルの3フロアを三井ホームグループの新しい拠点にすることが決まると、いよいよ「本社移転プロジェクト」が動き出す。三井デザインテック内にチームが作られ、プロジェクトを成功させるためには何が必要か、何度も話し合いが行われた。
「移転といっても各グループを1つの場所に集めるだけでは意味がありません。池田社長からも各社の繋がりが強まるように工夫してほしいとご要望がありました。また移転を機に、ABWなど新しい時代の働き方を具現化できる空間デザインを示すことも必要でした(営業・鈴木氏)」
三井ホームグループが今後目指す姿・新たな働き方を明文化していくことに関しては、コンサルティング担当の木村保之氏が役割を担った。
「2024年は三井ホームの創立50周年の年に当たります。そしてこのプロジェクトは三井ホームグループのこれからの50年を方向づけるものとして、グループ各社の集約を経てグループ連携の効果の最大化を目指していきたい、という事務局の皆様の並々ならぬ想いをうかがいました。その具現化のために、池田社長や役員の皆様とのディスカッションや、多くの社員の方々にご参加いただき現状の課題や新たな働き方を考えるワークショップを行いました。皆さまの想いから感じたのは、三井ホームグループの目指す姿をより具体的に浸透していく必要があること、そしてその実現に向けて様々な垣根を超えていきたいという皆さまの気持ちです」
本社移転プロジェクト」のコンセプトは「MOCXCOM(モクスコム)」。
三井ホームグループが打ち出している木造技術や事業の可能性を拡大するためのキーワードである(MOCX)の実現に向けて、新オフィスがその羅針盤(COMPASS)となることをイメージしている。次の50年に向けて、既存領域にとらわれず変化するために、個人の力・グループの力が既存領域を超えて重なり合うことを目指した。チームが話し合いを重ね、生み出した言葉である。
コンサルタントの木村氏と並走しながら空間を設計していったのは木村肇氏だ。「プロジェクトの方向性はコンサルタントの木村が導いてくれました。私はそこから新オフィスで実現したいことを整理していきました。ただスペースや予算の関係で要望のすべてを叶えられるわけではありませんし、また、すべての要望を盛り込めばいいというわけでもありません。最初に決めたコンセプトや概念に常に立ち戻り、本当に目指すべき空間のイメージを何度も共有し直すことが大切でした」




そして空間デザインの概念として用いられたのが「リビング イン アクセス」という考え方だ。グループ5社の執務エリアをルーム(ROOM)、共有エリアをリビング(LIVING)と捉え、各社のルーム(執務エリア)はリビング(共有エリア)を通ることでアクセスを可能とした。グループ5社の連携・交流の機会を増大させる配置である。デザイン担当の佐野翠氏は、グループ5社の交流を日常的に生み出す人の流れを何よりも大切にしたと語る。
「営業、コンサル、設計担当者からのバトンを受け取る形で、私たちデザイナーがプロジェクトに入りました。ただデザイン作業に入る前からチーム全員でミーティングを重ね、三井ホームグループの想いを反映させ課題を解決する新オフィスはどうあるべきかということをチーム全員で話し合ってきました。その中で導き出した答えは、リビング イン アクセス。家づくり、街づくりに関する高い知見を持つプロフェッショナルがそれぞれのルーム(執務エリア)を出てリビング(共有エリア)に集まり、コミュニケーションを深め、ディスカッションしながら、未来を創造していく。そんなオフィスにしたいと思いました」
「リビング イン アクセス」の考え方は、三井ホームグループが目指す新オフィスのあり方・働き方そのものだった。そしてプロジェクトのコンセプトである「MOCXCOM」を表現するために木材を各所に配置し、明るく気持ちの良いリビング(共有エリア)をデザインした。対してグループ5社のルーム(執務エリア)は、各社の業務内容や個性を大切に空間をデザイン。デザイナーの瀬尾翔氏が丁寧に要望を汲み取って、特色のあるルーム(執務エリア)に仕上げていった。
「リビングはみんなが気持ちのいい空間であるべきですが、だからこそルームはよりパーソナルな空間にしたいと思いました。住宅における部屋作りと同様に考え、各社の要望を反映させながらも、ブランドコンセプトである『MOCXCOM』から逸脱することのないようにルーム(執務エリア)のデザインを工夫しました。木材を使用したデザインだけでなく、地中に広がる木の根をイメージした仄暗い空間をデザインするなど、さまざまな角度から木の魅力を表現していきました」
リビング(共有エリア)とルーム(執務エリア)、それぞれ細部にまでこだわったデザインが施されているが、新木場オフィスのもっとも特筆すべき空間デザインはエントランスである。受付デスクの背後に広がるリビング(共有エリア)には木目調の材を大胆に組み合わせたスケルトン天井が広がり、「MOCX」を掲げる三井ホームグループの想いを象徴する空間となっている。訪れた人は皆、明るく気持ちの良いエントランスに圧倒されると思うが、受付デスクと共有エリアの間はセキュリティを配慮し、実はガラスで仕切られているのだ。ガラスの壁と床との境界線を見えにくくするなどの工夫を凝らし、ガラスの仕切りを感じさせないデザインとなっている。
「通常、社名サインは受付デスクの真後ろに配置します。しかし今回はガラス壁の奥、つまり天井に木が連なるリビング(共有スペース)の中心にあえて社名サインを配置しました。木の中心に社名サインを置くことで、“三井ホームグループが新たな木の世界を作っていく”という強いメッセージ性を持たせました(デザイン・佐野氏)」
「エントランスに自由でクリエイティブな共有エリアが広がっていることは、三井ホームグループの新しい働き方のアピールにもなります。こんな柔軟な働き方をしている企業なのかと、訪れた人は一目で理解するでしょう(設計・木村氏)」
新オフィスのコンセプトやデザインの概念が決まり、働き方に関するワークショップも重ねられていくと、三井ホームグループの中に新オフィスへの期待が徐々に高まっていく。三井ホームグループの技術者、デザイナー、商品開発担当者などと一緒にデザイン分科会を開催し、三井ホームグループならではの素材や意匠を新オフィスの空間に加えていくことが決まった。
「三井ホームグループと三井デザインテックのコラボレーションです。三井ホームグループが持つ高級感と技術や素材へのこだわりを新オフィスのデザインの中に落とし込んでいきました(デザイン・佐野氏)」
2024年2月、営業、コンサルティング、設計、デザインと最高のチームワークで進めてきたプロジェクトチームに最後のピースが加わる。工事担当の山本佑輔氏だ。工事の完了予定は5月。各所に散らばった三井ホームグループ5社の引っ越しと800人規模の移動を考えると、約3ヶ月間の工期は通常では考えられない短さだった。それでも管理体制を工夫したり工程の順番を組み変えたり、工期短縮のためにやれることはすべて試した。
「工事に入る前に行った施工会社向けの説明会では、工期の短さに厳しい意見も出ました。しかし工事のプロとして、決められたスケジュール通りに仕上げたいという気持ちがありました。今回は通常の3倍近い約60社の施工会社が工事に参加したのでやりとりが大変でしたが、工事側からの相談に対するチームからの判断も、三井ホームグループからの回答も早かったので途中で滞ることなく工事を進めることができ、とても助かりました」
プロジェクトの規模からするとかなりタイトなスケジュールではあったが、結果的にはマスタースケジュール通りに進めることができた。その理由はチームワーク。三井デザインテックではプロジェクトごとにチーム構成が変わるが、このプロジェクトに集まったメンバーには、自分たちの役割・領域を超えてお互いを支え合い連携しようとする意識がとても高かった。そしてこの最高のチームワークは三井ホームグループにも伝播した。三井デザインテックと三井ホームグループが一体となって、目指すべきオフィスと働き方を共に創造していくことができた。サステナブルな社会の羅針盤として木造の可能性を追求する三井ホームグループの新しい50年は、このオフィスから始まっていくのだ。
※新木場センタービルに本社移転した三井ホームグループ5社(三井ホーム、三井ホームリンケージ、三井ホームエンジニアリング、三井ホームエステート、三井ホームデザイン研究所) 三井ホームグループ5社の名称は2024年6月時点のもの




【コンサルティング】
スペースデザイン事業本部ワークスタイルデザイン室
コンサルティング第2グループ
木村 保之
【設計】
クリエイティブデザインセンター
ワークプレイスデザイングループ
木村 肇
【営業・PM】
スペースデザイン事業本部
オフィスデザイン事業2部 新宿営業グループ
鈴木 達也
【デザイン】
クリエイティブデザインセンター デザイン第6グループ
佐野 翠、瀬尾 翔
【工事】
スペースデザイン事業本部
オフィスデザイン事業2部 新宿工事グループ
山本 佑輔
interviewer&text / Yasuko Hoashi
photo(竣工写真) / Nacása & Partners Inc.
(インタビュー写真) / Teruyuki Yoshimura