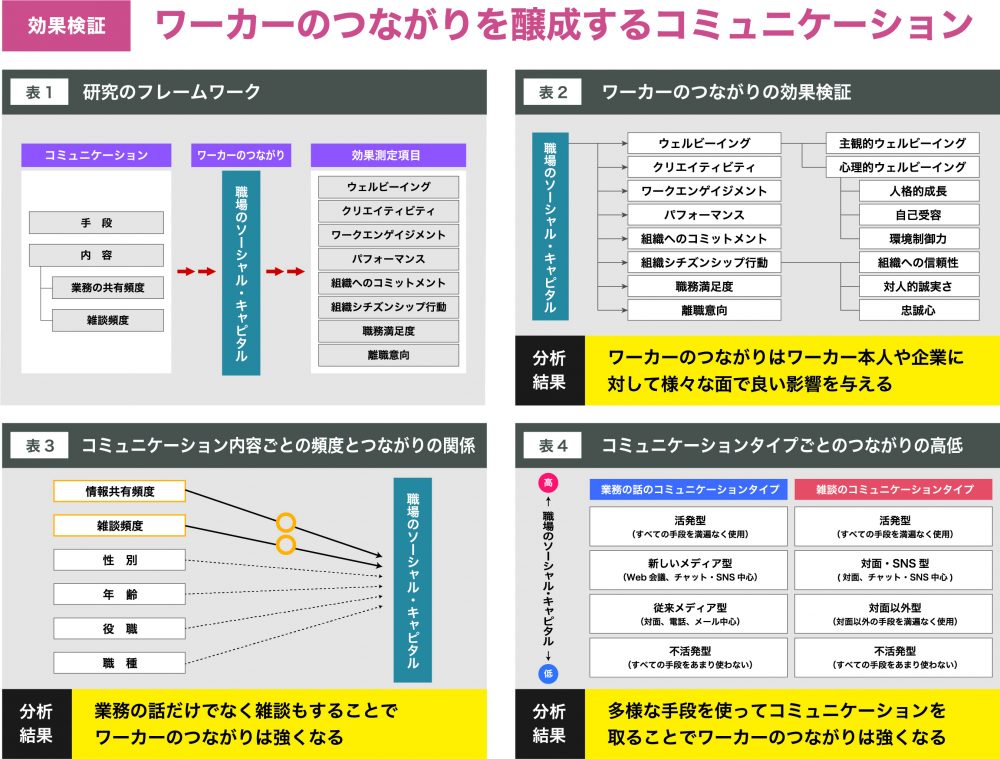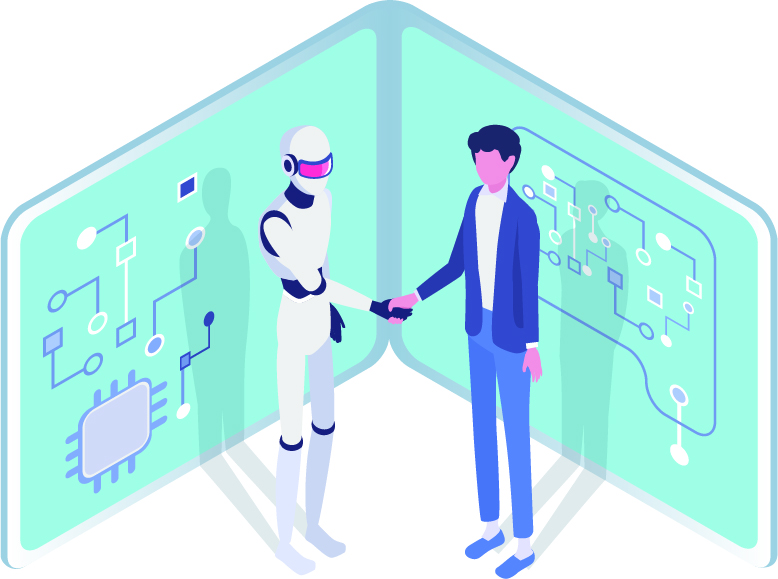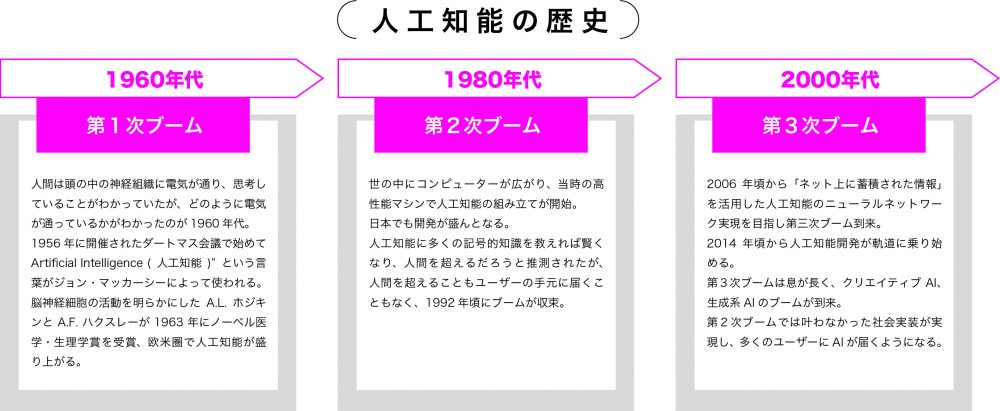- contents
-
- Future Articles
- New Relationships
- Offistyle+
Future Articles
- vol.18
-
RX Japan Ltd.
さあ、行こう。新たな軌跡を創る旅へ
RX Central Station
「世界を拓くビジネスの舞台を。」
そんな熱い想いで世界と向き合う展示会の主催・運営会社のオフィスは、
どんなデザインであるべきなのか。
オフィス移転にあたり新しい働き方と働く環境を模索するRX Japanと
三井デザインテックのソリューションが、日本の中心である東京駅を舞台に共鳴する。
常識にとらわれない要望にコンサルティングとデザインで応えていった三井デザインテックは、オフィスデザインに新たな風を吹き込んでいく。

三井デザインテックとRX Japanとの信頼関係の構築は、RX Japanがまだ新宿にオフィスを構えていた2021年6月に遡る。この時は受付エリアのみの改修依頼で、いわば三井デザインテックへのトライアルとしての発注だった。オフィス全体のデザインから施工までトータルで手掛けることを得意とする三井デザインテックとしては、当初は戸惑いもあった。しかし、日本一の展示会主催・運営会社が使命として抱く「世界を拓く ビジネスの舞台を」という熱い想いに触れ、「この会社で働く人たちが気持ちよくクリエイティブに働ける空間を提案したい」という気持ちを強くしていった。「RX Japan 新宿オフィス18F改修プロジェクト」チームの一人でコンサルティング担当の桜林玲佳氏が当時を振り返る。「2021年といえばまだコロナ禍で、テレワークというワークスタイルを選択する人も多くいました。だからこそオフィスに来る意味をしっかりと提案したいと思ったのです。コロナ禍をきっかけに在宅やシェアオフィスで働く人も増えましたが、オフィスには社員同士のつながりを醸成するという他の場所にはない価値があります。そのオフィスの顔であり、中心でもある受付エリアを社員同士のコミュニケーションが活性化するエリアにしようと想いました」
RX Japanとの話し合いを経て、働く環境を自由に選択できるフレキシブルさと領域を超えたコラボレーションが加速するワークスタイル・ワークプレイスの創造へと動き出す。プロジェクトを進めるにあたり、デザイン担当の藤本裕助氏はRX Japanの意思決定の速さに驚いたという。
「最初の提案から施工を始めるまでの期間は約2ヶ月間しかありませんでした。短期間で仕上げるためにはスケジュール管理が大切なのですが、こちらの提案に対するRX Japanの判断がとても速く助かりました。期間や予算の面で設備や躯体に関わるところは変更できませんでしたが、やるからには喜んでもらえる空間にしたかった。その想いがプロジェクトの評価につながったのだと想います」
クリエイティブな企業にふさわしい自由で明るい印象の受付エリアをデザインし、社員のコミュニケーションエリアとしても創造性を高める場所として好評を得た。人を驚かせたい、感動させたいというRX Japanの企業文化に、空間デザインという形で三井デザインテックが応えたのだ。そしてこのトライアルの成功が三井デザインテックとRX Japanの信頼関係を強くし、東京・八重洲の移転プロジェクトへと進んでいく。「RX Japan 新宿オフィス18F改修プロジェクト」から「RX Japanオフィス移転プロジェクト」まで営業として担当した相庭武瑠氏は、両社が共鳴し、とても良い関係性を築けた案件だったと語る。
「新宿オフィス改修のトライアルで評価を得ることができ、八重洲新オフィスへの移転にも関わることができました。新宿も八重洲も設計デザインのみの提案で、コンサルから施工まで手掛ける三井デザインテックの通常の仕事の進め方とは大きく異なり、また期間も短かったため、コンサルタントやデザイナーは苦労したところもあったと想います。それでも、新宿オフィスの改修で培ったRX Japanとの信頼関係がありましたし、こちらが提案したことへのレスポンスも速かったので、全般的にスムースに進んだように想います」
RX Japanの八重洲新オフィスへの移転に向け、チームが再び動き出す。しかし提案から竣工までの時間はわずか9ヶ月間しかなかった。提案から施工を始めるまではさらに短い。限られた期間の中でスムースに進められた要因は、やはりRX Japanの速い意思決定にあったと藤本氏は語る。
「どんな新オフィスにしたいか、RX Japanの考え方ははっきりしていました。人を驚かせたい、感動させたいという想いです。そのために設備設計に関わる壁の位置について意志が明確でした。オフィスの骨格が早めに決まったので、デザインも進めやすかったです」
移転プロジェクトからチームに加わったデザイナーの杉山香織氏は、主に意匠部分を担当した。彼女もまた、RX Japanの新オフィスへの想いを強く感じたという。 「RX Japanの社長から強く言われたことは、ここを訪れたお客さんがメインエントランスに入った瞬間に“ワォ!”と言わせたいというものでした。メインエントランスから続くラウンジスペースにも仕切りを作らず、まっすぐに伸びた空間の先からは東京駅が一望できるビューを確保し、訪れる誰もが感動する空間を作ってほしいと言われました。エントランスにこんなに広い面積を取ることは通常はありません。珍しい要望でしたが、それだけ新オフィスへの明確な想いがあると感じましたし、その想いに応えたいと想いました」
移転プロジェクトには、最初はコンサルティングの契約はなかった。しかし、空間だけでなく働き方そのものをデザインする三井デザインテックのソリューションを深く理解していたRX Japanでは、より良いオフィスを作るために、設計デザインだけでなく、コンサルティングの契約も決めた。再びチームに入った桜林氏は、RX Japanの移転プロジェクト担当者に三井デザインテック本社オフィスを見てもらうことで、働き方や働く環境のトレンド、理想のオフィス空間のイメージを共有してもらおうと考える。

ここからRX Japan と三井デザインテックの協創が始まった。

好評だったため移転プロジェクトでもリラックスエリアの中に取り入れた。

コーヒーマシーンなどが用意されており、社員同士のコミュニケーションを深めることに役立っている。

社員同士がカジュアルにコミュニケーションが取れる空間を目指した。
「普段であれば、発注元の企業さまとワークショップを重ねながら新オフィスのコンセプトを作っていくのですが、今回は時間が限られていましたので、三井デザインテック本社に来てもらうことを優先しました。オフィス見学を通して自由な働き方や働く環境のトレンドに触れたことで、RX Japanの皆さんの中に、自分たちはどんなオフィスを求めているのかという方向性がはっきりとしていったように想います」
オフィス移転プロジェクトのコンセプトは「RX Central Station」。日本の中心地、東京駅を舞台にさらなる高みへ飛躍する。個性が交差し、才能を開花させる。そんなイメージを内包させた。そして桜林氏はコンサルタントとして、コンセプトを具現化させるためのワークショップを加速させていく。
「コミュニケーションエリアの一角に特別なコミュニケーションの場を創るために、RX Japanの皆さんとワークショップを行いました。コミュニケーションエリアは社員同士の一体感を育むエリアです。そのコミュニケーションエリアの中でも自分たちにとって特別な空間を創るとしたら、どんな机や椅子が欲しいか、そして形や色、素材は何がいいのか、意見を出してもらったのです。さらにそのエリアに名前をつけることも提案しました。ワークショップに参加した社員の方に候補となる名前を考えてもらい、投票で決めました。ワークショップを通してオフィス移転を自分事化したことで、社員の皆さんの新オフィスへの愛着を高めることができたと思っています」
藤本氏と杉山氏は「CENTRO(セントロ)」と名付けられたコミュニケーションエリアの一角に向き合う形で、重ねながら新オフィスのコンセプトを作っていくのですが、今回は時間が限られていましたので、三井デザインテック本社に来てもらうことを優先しました。オフィス見学を通して自由な働き方や働く環境のトレンドに触れたことで、RX Japanの皆さんの中に、自分たちはどんなオフィスを求めているのかという方向性がはっきりとしていったように想います」 オフィス移転プロジェクトのコンセプトは「RX Central Station」。日本の中心地、東京駅を舞台にさらなる高みへ飛躍する。個性が交差し、才能を開花させる。そんなイメージを内包させた。そして桜林氏はコンサルタントとして、コンセプトを具現化させるためのワークショップを加速させていく。 「コミュニケーションエリアの一角に特別なコミュニケーションの場を創るために、RX Japanの皆さんとワークショップを行いました。コミュニケーションエリアは社員同士の一体感を育むエリアです。そのコミュニケーションエリアの中でも自分たちにとって特別な空間を創るとしたら、どんな机や椅子が欲しいか、そして形や色、素材は何がいいのか、意見を出してもらったのです。さらにそのエリアに名前をつけることも提案しました。ワークショップに参加した社員の方に候補となる名前を考えてもらい、投票で決めました。ワークショップを通してオフィス移転を自分事化したことで、社員の皆さんの新オフィスへの愛着を高めることができたと思っています」 藤本氏と杉山氏は「CENTRO(セントロ)」と名付けられたコミュニケーションエリアの一角に向き合う形で、人事や総務などの企業管理部門のエリアをデザインした。社員が集まるエリアの近くに企業の事務管理を司る部署を配置することは、セキュリティ的にも一般的ではない。しかしRX Japanは、そんな常識よりも社員同士のコミュニケーションの大切さを選んだ。そして現在、普段は交わらない部署の間でコミュニケーションが生まれ、新たなクリエイションにつながっているという。杉山氏は「管理部門は今まで壁で区切られた部屋の中にありましたが、あえて社員エントランスから入ってすぐのカフェエリア(Centro)の前に配置することで必ず顔を合わせることになります。管理部門には役員様を含め全ての部署が頻繁にアクセスするので、他部署との交流が移転して数日後には数倍になったと聞いております。これは計画時に考えていた以上に、とても面白い化学反応でした」と感想を述べた。
そして藤本氏は、三井デザインテック本社のオフィス見学がRX Japanにさまざまな刺激を与えることができたのではないかと振り返る。
「RX Japanの皆さんはオフィス見学の際、表面的な意匠デザインに着目するのではなく、自由な働き方や働く環境そのものを取り入れたいと感じてくれました。その結果、コミュニケーションエリアの考え方はもちろん、ABW(Activity Based Working)の一つの形として執務エリアに“ホームタウン”という考え方を取り入れました。このエリアは部門と部門の間に存在させるスペースで、フリーアドレスで使用できます。仕事内容に合わせて自由な使い方ができます。部門ごとのコミュニケーションを広げることにも役立つでしょう。ホームタウンは新オフィスの大きな特徴となりました。今回、“世界を拓くビジネスの舞台を”という熱い想いに寄り添って新オフィスをデザインできたことは、とても刺激的でした。オフィスは生き物。時代に合わせて進化していく必要があります。展示会から時代を創るクリエイティブな企業に相応しいアップデートを、これからもお手伝いしていきたいと思っています」
「RX Japan 新宿オフィス18F改修プロジェクト」と「RX Japanオフィス移転プロジェクト」の2つのプロジェクトは、三井デザインテックとRX Japanとの信頼関係を強固にしただけではなく、常識にとらわれないさまざまな試みを通して、オフィスデザインに新しい風を吹き込んだように思う。両社の共鳴が創り出したRX Japanの新オフィスが、日本から世界に羽ばたくためのCentral Stationとして多くの人たちを刺激していくことを期待したい。
interviewer&text / Yasuko Hoashi

3連のプロジェクターや大型LEDモニターを活用し様々なプレゼンテーションが可能。
リモート会議環境も充実しており、遠隔でもその場にいるような臨場感ある音響設備を導入。

様々なプレゼンテーションや、イベントに活用できる。

デジタル機器の使用を優先せず、あえてデジタルデトックスな空間にしている。

奥の丸テーブルで立ったままで仕事をするのだそうだ。
中央に配置されたテーブルは役員ミーティングや社員とのカジュアルミーティングに使う。