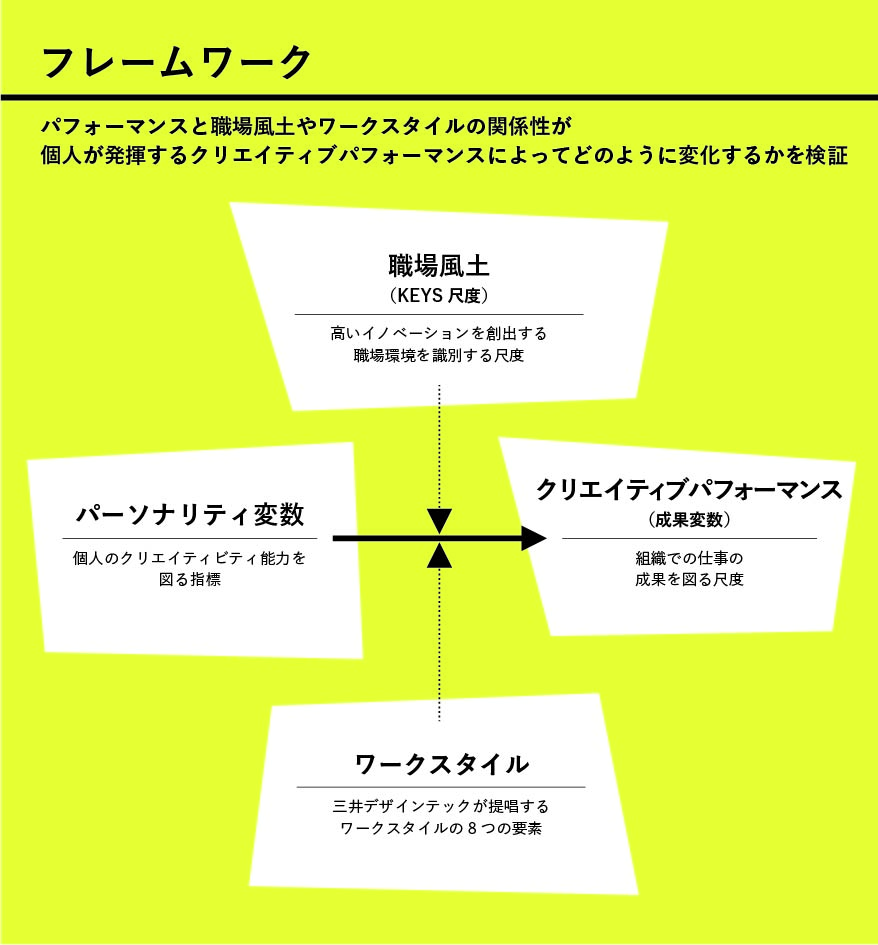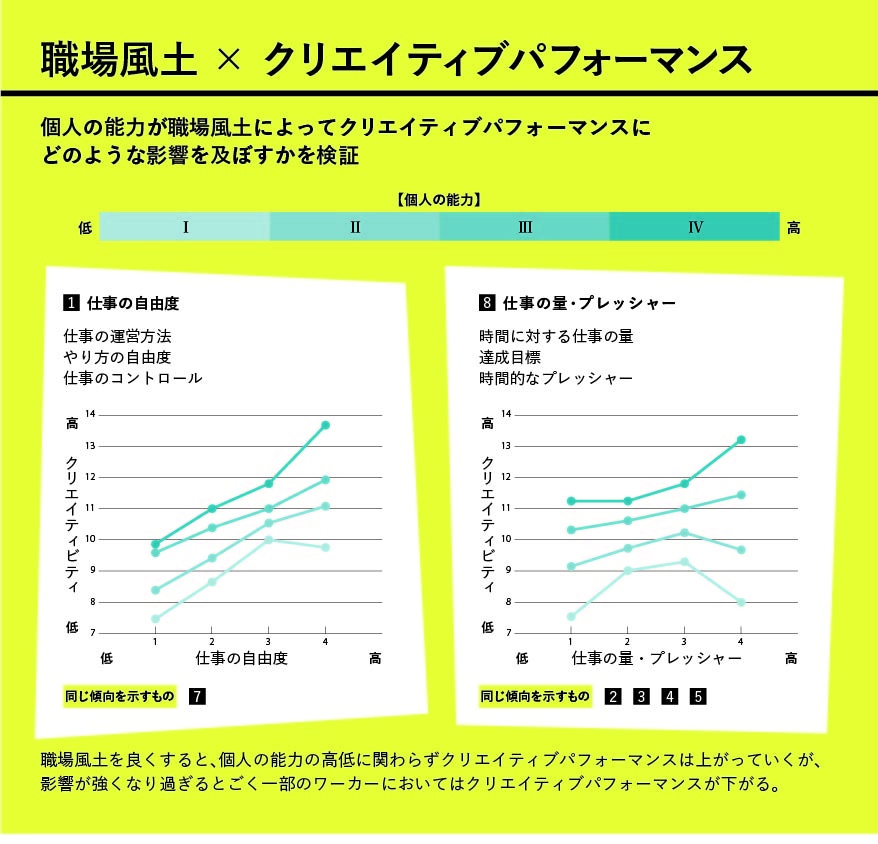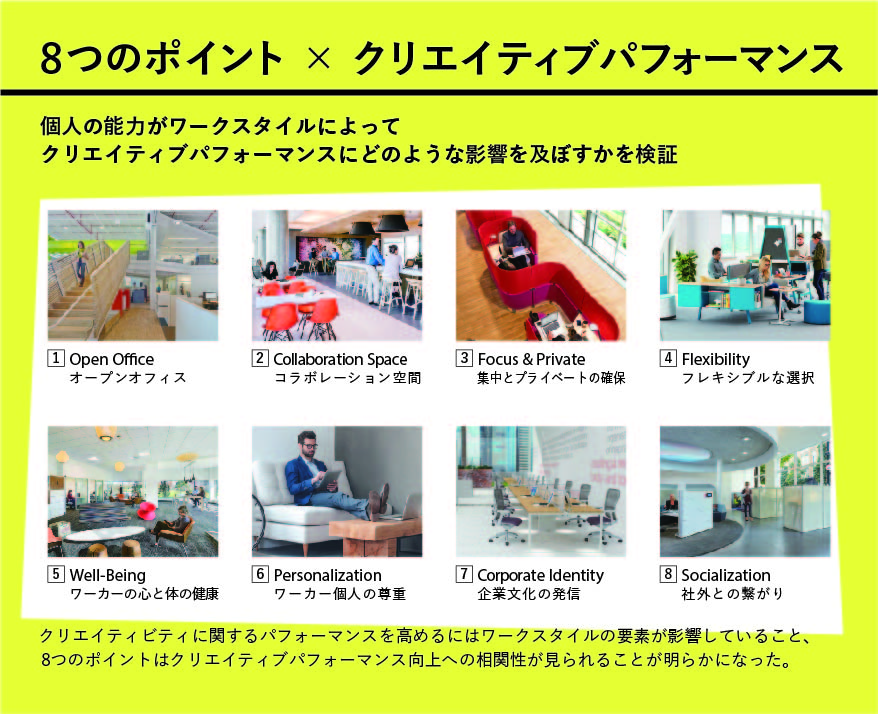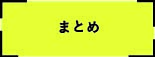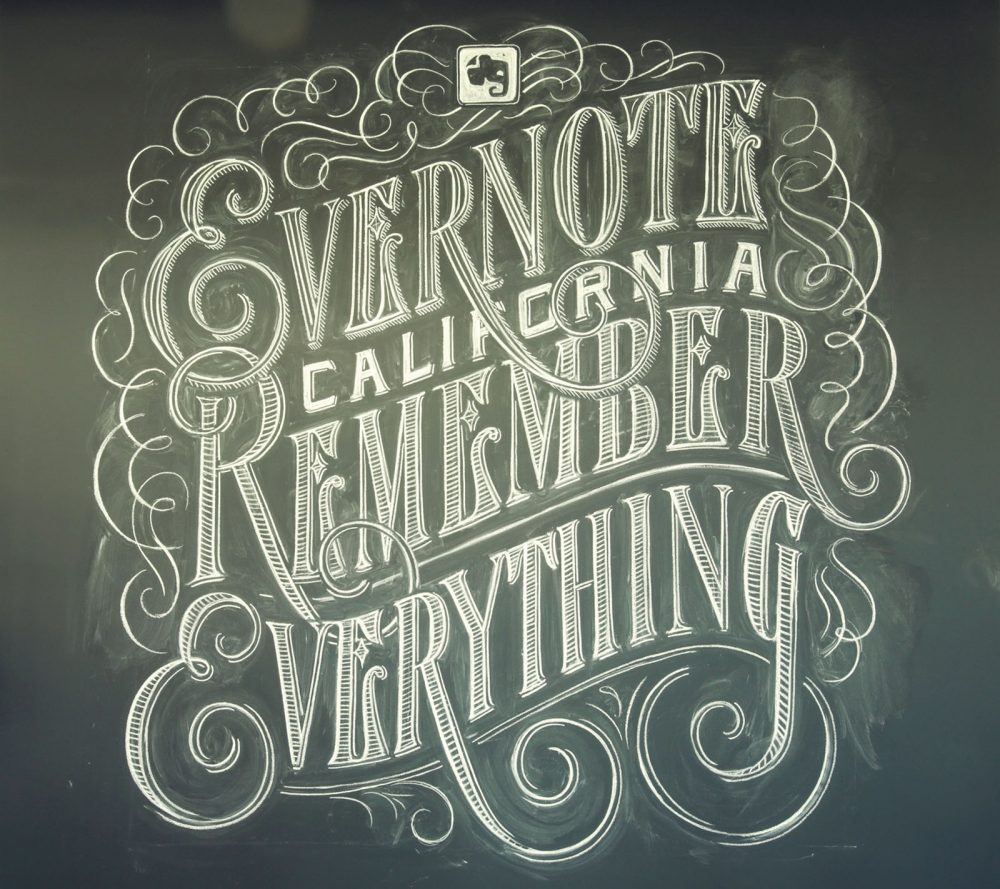- contents
-
- Future Articles
- New Relationships
- Offistyle+
Future Articles
- vol.9
-
WORKPLACE STRATEGY
Calder Consultants Pty Ltd
三井デザインテック株式会社は、オーストラリアのワークスタイル関連コンサルティング企業
Calder Consultants Pty Ltd(本社:ビクトリア州メルボルン、ファウンダー:James Calder、以下Calder社)と
業務提携し、本年6月1日より本格的に活動を開始いたしました。
三井デザインテックはCalder社の保有するさまざまなデータやノウハウと、自社が持つ国内のオフィス環境や
ワーカーに関する情報を活かすことで、先進的かつ日本に適したオフィスコンサルティング活動を行ってまいります。
また、創業者でありワークスタイル専門家のCalder氏がスピーカーを務める勉強会やセミナーを開催するなど、
働き方改革に関するコンサルティング事業の強化をしていく予定です。
本誌『Offiche』では、「次世代の日本のオフィス」をテーマに、
数回に渡って読者のみなさまにCalder氏の連載記事をお届けいたします。

フローについて
日本の企業は、業務プロセスのスピード化、個人とチームによる高いパフォーマンスの創出のために、障害となりうるさまざまな壁を取り払おうとしています。現状多く見られる、サイロ型と言われる縦型構造の旧態依然の組織モデルや、重層型ヒエラルキーの中で管理する経営スタイルでは、競争力を保つことが難しくなってきています。日本で問題となっている長時間労働、過剰な残業時間により組織の非効率さを改善することはもはや困難と言えるでしょう。
日本の企業が組織改革に取り組み、より効率的なワークスタイルやそれを実現するためのさまざまなテクノロジーを採用し始める一方、見落とされがちなのが、オフィスの物理的な構造が変化の実現を妨げているという事実です。多くの日本のオフィスは、フロアごとに社員を分け、まるで工場で生産される装置一式のパーツであるかのように、効率性を重視し、高密度に収容することを目的とした場所として設計されています。そうしたオフィスは、すでに今の時代を生きるワーカーにはそぐわないものになってきています。昨今の仕事の多くはダイナミックに相互交流し、市場へのスピーディーなアクセスが求められます。オフィスでは、ワーカーのインタラクション(相互作用)をより高めるため、デスクだけにワーカーが留まらない工夫から、オフィスビル自体をどうデザインするかまで考え直さなくてはなりません。今、最もオフィスに必要とされていること、それは“フロー(流れ)”です。
私たちはオフィスビルやオフィス内スペースを、フローを促進するものとしてデザインしなくてはなりません。オフィスビルの建築、オフィススペースのインテリアデザインや家具、そして人員やスペースの計画、これらは簡単に変えられるものではありません。何十年と使うインフラに多額の投資をするための明確なビジョンを創ることには非常に時間もかかるでしょう。
次世代のオフィスに求められるフローは、社員のサーキュレーション(循環)を水平方向(同一フロア)にも垂直方向(上下フロア)にも四方八方へどのように生み出すか、またリアルタイムでチームの変化や適正配置を促すか、そして新しいアイディアをいかに生み出すか、といったさまざまな要素があります。オフィスの環境はこうしたさまざまな要素をふまえ、フローを容易にするためにデザインされなければなりません。
一般的な日本のオフィスビルは構造的にシンプルで、機能的な設備計画を考え、賃貸可能なエリアを最大化することを最優先に設計されています。またオフィス内においても、ワーカーの動線通路を最小限にし、効率的にデスクや個室を配置することが重要視されています。
しかし、「フローの視点」でデザインする時にはまったく別なロジックが必要になります。ワーカーが循環するためのスペースには、単なる動線通路としての効率性よりも、視覚的な意味合いやワーカーのつながる要素が優先されます。 そこで働く人たちが、相互交流型の繋がりを持てること、それが最も重要なのです。現代において、人々がオフィスに働きに来る最大の理由は、互いに関わり合いを持つためです。今、オフィスの設計に必要なのは外側から先にデザインして内側をそれに合わせる「外から内へ」のデザインでなく、内なるニーズに合わせて「内から外へ」とデザインすることです。

オフィスビルにおけるフロー
フローをつくり出すためには、まずエントランスから始めます。企業は、顧客と親密な繋がりを築けるように自分たちの商品やサービスを発信する必要があります。次世代のオフィスビルでは、ロビー階や低層階を顧客との接点として使用するとよいでしょう。
例えば、小売業であればリアルストアをロビー階に設け、従業員はオフィスフロアに行くためには顧客に交じってその中を通っていきます。 顧客だけでなくさまざまなパートナーとコラボレーションできるスペースを設けます。銀行のオフィスであれば“未来をイメージした銀行の支店”をロビーフロアに設けるのも面白いでしょう。合わせて、中小企業経営者のためのコワーキングスペースも設けます。さらに、大きなイベントを行うためのアトリウムやギャラリースペースもつくり、どのようなコミュニティでも自由に使えるようなスペースにします。エントランスでは、できるだけ抽象性を排除し、丁寧に企業のブランディングを表現していきます。そして、パブリックスペースとオフィスのスペースの境界はできるだけなくします。
セキュリティを通過した後の動線は、シンプルで直感的な動きを妨げないものにします。 また、吹き抜けを活用し、大きなスペースを視覚的に繋げ、階段を適切な位置に設けることで垂直な動きも生み出します。
理想的なエレベーターの配置は1ヵ所にまとめることです。そうすることによって、フロア内のさまざまな場所に分かれて座っていた人たちの動線がまとまり、相互交流を促進することに繋がります。オフィス内スペースは、機能的なゾーン分けを行い、ヒューマンスケールに合わせたチームのためのスペースを設けます。人と人が出会う場所には、コミュニケーションのために滞在できるスペースやアメニティ機能を設け、最大限にセレンディピティを生み出す仕掛けを組み込みます。
チーム・フロー
ハイパフォーマンスを実現するオフィスにとって最も重要なのがチームのためのスペースです。パフォーマンスが高いチームは、活動的で能動性が高く、コラボレーションやマルチスキルに長け、クリエイティブな働き方をします。こうしたチームは、状況によりその形態もメンバーもさまざまに進化します。そのため、スペースもチームのニーズや用途に合わせてその都度変化したり、アレンジしたりできるフレキシブルなものでなければなりません。
また、アイデアを書きとめるホワイトボードやピンボードを周囲に配置し、それらは即座に動かしたり配列を変えたりできるようにします。最新のテクノロジーを組み込むことも重要です。
フローの高いチームの一例は、ICT企業に見られます。ICT企業では、アジャイルプロセス(迅速かつ適応的にソフトウェア開発を行う軽量な開発手法群の総称)を採用したチームでリアルタイムにハイスピードでソフトウェアを開発していきます。ホワイトボードやスタンドアップミーティングスペースやさまざまな形態のコラボレーションスペースを活用して、即興的にコミュニケーションを取っています。
パーソナル・フロー
周到な計画を練ることなくつくられたオープンプランのオフィスでは、多くの不満を耳にします。それはいろいろなことが仕事を中断するからです。集中したフロー状態であれば、15分でできる仕事を妨げられてしまうことにより非効率となるからです。集中したフロー状態であれば通常より5倍もパフォーマンスが向上するという報告もあります。高い集中を経験すると感覚的な時間の流れが変わったように感じます。
必要な時に、こうしたフロー状態をつくり出せるようにすることが重要です。高い生産を生み出すことは、幸福感と健康的でより高い自己肯定感につながります。
フロー状態を実現するのに必要な環境は、人それぞれ異なります。 カフェの中でヘッドフォンをした状態が集中しやすい人もいれば、防音の効いた静かな部屋が必要な人もいます。当然ながら、ハイパフォーマンスを生むためのチームに必要な要素と、個々人がフロー状態を生む要素との間には軋轢が生じます。オープンプランのオフィスも、そして旧来の島型レイアウトや、個室型レイアウトのオフィスもこの難題を解決することはできませんでした。しかし、次世代のオフィスは、理想的なさまざまな要素を用意し、使いたい時に即座に使えるようにします。
フローの測定
フロー状態が増えたかどうか、測定することは意外に簡単です。ミーティングの時間は短くなり、明確な目的のために即興的に少ない人数で行われるミーティングが増えていきます。メールの数は減り、オフィス内の人の動きが増加します。社員の幸福度と健康状態が向上し、会社への帰属意識までも向上していきます。また、マーケットにスピーディーに反応できるようになり顧客の満足度も上がります。こうしたオフィスに勤務している人たちは、口々に、目の前のタスクに集中することができて、障害がなく目的を達成できることの喜びを口にします。また管理職の人たちはリアルタイムでマネジメントにあたることができるようになります。
次世代の日本のオフィスは、そこを占有する人たちに、より良いフローを生み出すことで、莫大な経済的価値を生み出すことになるでしょう。
ジェームス・カルダー


- 関連リンク
-
- Offistyle+
- アジャイルワーキングの歴史と未来
- Offistyle+
- 脱企業型(un-corporata)ワークプレイス